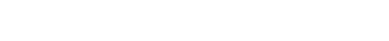「From Seed to Cup」――それは、生産地からカップに届くまでの一杯の物語。では、その生産地が、遥か海の向こうだけでなく、日本国内にも広がったら? 国産コーヒーの生産・商品化を目指す、味の素AGF社の「徳之島コーヒー生産支援プロジェクト」。コーヒー消費国として知られる日本に、生産地としての文脈が加わるコトで、私たちのカップに映る景色はどのように変わるのでしょうか?

島のもう一つの顔
鹿児島県本土から南へ約500キロ。南西諸島の奄美群島に属する徳之島は、観光開発のされていない豊かな自然と素朴な南の島の文化が味わえる、日本でも希少な離島だ。その豊かな自然と独自の生態系から、2021年には世界自然遺産にも登録され、将来的な観光業の成長が期待されている。そして今、徳之島のさらなる発展の追い風として、ある飲み物が注目を集めている——それが、私たちが愛してやまないコーヒーだ。しかもカフェやコーヒーショップといった消費の文脈ではない。この島は今、国産コーヒーの生産地として名乗りを上げているのだ。
「他の国内のコーヒー産地と比べて特徴的なのが、ビニールハウスを使用せず、露地栽培を行っている点です。ビニールハウス栽培では暖房設備が前提となり、エネルギーコストがかかりますが、露地栽培なら気候の影響を受ける反面、環境負荷が少ない生産を実現できる。年間の収穫量はまだ数百キロ程度ですが、着実に成果は出てきていますよ」
そう話すのは、味の素AGF株式会社(以下、AGF社)で「徳之島コーヒー生産支援プロジェクト」の主担当を務める臼井孝允さん。2017年に、徳之島コーヒー生産者会、伊仙町役場、丸紅株式会社、AGF社が共同で立ち上げた同プロジェクトは、徳之島で国産コーヒーの生産・商品化を目指す試みだ。活動拠点である伊仙町のコーヒー生産者組合には、現在30以上の農家が所属しており、その多くはサトウキビやジャガイモ栽培を並行して行う兼業農家である。島は温暖多雨の亜熱帯性海洋気候で、雨季と寒季の区別がなく、開花やチェリーの成熟時期がばらつくため、収穫はすべてハンドピックで行われる。
「徳之島ではもともとティピカ、モカ、イエローブルボンなどの品種が植えられていましたが、近年は台風の影響を考慮し、背丈の低いサルチモールといった矮性種の栽培にも取り組んでいます。収穫期に雨が降ることも多いため、精製方法には天候の影響を受けにくいウォッシュトプロセスを採用しています」



サンゴ礁の上に実る可能性
国産コーヒー事業のきっかけとなったのは、AGF社が2015年に発表したコーヒーブランド「煎」だ。日本の軟水に合った“ジャパニーズコーヒー”を追求したこのブランドは、市場で大きな反響を呼び、社内の次なる目標として、国産のコーヒー豆を使用した「真のジャパニーズコーヒー」の商品化が掲げられた。
「日本国内のコーヒー産地を調べる中で出会ったのが、徳之島で40年以上コーヒー栽培に取り組んでいた故・吉玉誠一さんでした」と、プロジェクトメンバーであるAGF社の塩尻敦史さん。「吉玉さんはもともとブラジルへ移住し、農業をしたいと考えていましたが、家族の反対もあってその夢を断念。その後、サトウキビ栽培のために徳之島を訪れた際に、中南米原産のキャッサバが育っているのを見て、とても驚いたそうです。そして『キャッサバが育つなら、同じ熱帯作物であるコーヒーも育つのではないか』と考え、コーヒー栽培に乗り出しました」
吉玉さんが中心となり、2000年には徳之島初のコーヒー生産者組合が設立。一時は台風被害でコーヒーの苗が全滅するという危機にも直面したが、2017年にAGF社のプロジェクトが発足され、国産コーヒーの栽培が本格化する。だが、新たなコーヒー生産地の開拓は決して簡単な道のりではなかった。
最大の障壁となったのが、島の土壌環境だ。徳之島はサンゴ礁が隆起してできたため、土壌は弱アルカリ性。弱酸性の土を好むコーヒーノキにとって、島の土壌は栽培に適しているとは言えない。また、栽培エリアの標高はわずか100mほどのため、チェリーの密度が上がりづらい傾向がある。「通常の生産地では収穫までは3年ほどですが、徳之島では土壌や気候の影響から、最低5年はかかります」と臼井さん。「だから、短期的な成果ではなく、時間をかけ、着実な一歩を踏み続けることが大切なんです」



生産を知れば消費が変わる
AGF社による国産コーヒーへの挑戦は、単なる社内事業の枠組みを超え、島の未来を支える取り組みへと広がりつつある。プロジェクトが展開される伊仙町は、過去50年間で島の人口が約半減するなど、深刻な過疎化に直面している。現在、高校を卒業した島の若者の8〜9割が本土へ進学・就職し、農家の大半が60〜70代を占める徳之島において、人口減少は島の基幹産業である農業の存続に直結する課題となっている。こうした状況の中で、若者のUターンや新規就農者を増やすには、島の魅力向上や雇用創出とともに、若者が将来を託せる新たな基幹産業の確立が不可欠。徳之島でのコーヒー栽培は、その鍵を握る重要なプロジェクトなのだ。
「2024年末に徳之島コーヒーが初めて商品化に成功したこともあり、島を訪れる観光客やコーヒー栽培に関する問い合わせも増えています」と、島のコーヒー農家である時任かおりさんは話す。時任さんは、高校進学と同時に島を離れ、本土で看護師としてキャリアを積むが、親の介護などをきっかけに2022年に島へUターン。その翌年、伊仙町役場が企画したコーヒーイベントに参加したことをきっかけに、新規就農者として伊仙町でコーヒー栽培を始めた。
「私のような農業未経験者がコーヒー栽培を始められたのも、AGF社が開催する研修や国産コーヒーの栽培実践塾など、充実した支援体制のおかげです。徳之島のコーヒー産業の発展には、何よりコーヒー生産者の増加が欠かせません。現在は、新規就農者が安心して挑戦できるよう、生産者同士が情報を共有し、支え合える体制づくりに取り組んでいます」
これまで、日本のコーヒー文化における「From Seed to Cup」は、遥か海の向こうの生産地を前提としてきた。だが、徳之島のコーヒー産業が発展し、日本が生産国としての顔を持つようになれば、スペシャルティ市場に限らず、国内のコーヒー消費のあり方は大きく変わる。それは言い換えれば、コーヒー市場における「モノ消費」から、物語や体験価値を重視する「コト消費」への移行だと、AGF社の塩尻敦史さんは説く。
「昨今、コーヒー価格は急上昇していますが、生産の現場を知らなければ、単なる値上がりととしか思えません。しかし、実際に徳之島を訪れて、コーヒーの生産にあれだけ手がかかることを目の当たりにすれば、一杯のコーヒーに対する価値観は大きく変わるはず。コーヒーの2050年問題をはじめ、世界のコーヒー需給がさらに厳しくなる中で、生産の現場を訪れ、コーヒーの物語に触れる機会は、今後ますます重要になっていくでしょう」



コーヒーアイランドを目指して
徳之島では毎年、コーヒーの収穫期に島をあげて収穫祭が開かれる。今年2月の収穫祭には、AGF社がメインスポンサーを務めた焙煎競技会「1st Crack Coffee Challenge」の優勝者や関係者が島を訪れ、チェリーの収穫や焙煎、コーヒーの試飲を行った。
「コーヒーは、スパイシーさと甘さがしっかりとあるという印象でした。焙煎は少し長めに焼いて、深めに仕上げると良いですね。単体でも美味しいし、ボディがしっかりしているので、ラテなどのミルクとの相性も良いと思います」。そう語るのは、ギーセンジャパン代表・福澤由佑さん。徳之島の生産現場を訪れた福澤さんは、国産コーヒーの将来性に大きな期待を寄せる。
「徳之島のコーヒーが本土でも広がれば、日本の消費者の関心も高まり、実際に生産地を訪れる人も増えていくはずです。たとえ高価格帯であっても、国産のコーヒーに投資したいという消費者は少なくない。将来的に収穫量が増え、コーヒーショップに国産のトップロットとデイリーロットが並ぶようになれば、業界全体のボトムアップにもつながると思いますね」
徳之島でコーヒー生産の土壌ができつつある今、AGF社が目指すのは、「収穫量の拡大」と「品質向上」だ。徳之島産コーヒーは、その希少性ゆえに高値で取引されるが、今後生産が拡大すれば、価格の変動が予想される。そこでAGF社は、島の農家向けに、加工過程における欠点豆のピッキング指導や土壌改善のセミナーなどを通じて、高品質なコーヒー生産に向けて取り組んでいる。彼らが目指すのは、高品質で高価格帯の国産スペシャルティコーヒーの実現だ。
社内事業の一環として始まった徳之島のコーヒープロジェクトはいま、島の未来、そして日本のコーヒー消費の未来を見据えている。先の見えない長い挑戦の旅路の中で、AGF社の塩尻さんによると、プロジェクト関係者の間では、ある一つのビジョンが共有されているという——それは、徳之島がコーヒーアイランドになる未来だ。
「いつか徳之島が、コーヒーの生産、加工、消費のすべてを体験できる場所になってほしいと、プロジェクトメンバーはいつも話しています。収穫体験はもちろん、島の各地に焙煎拠点があり、収穫した豆を自分好みに焙煎して味わえる、というコーヒーツーリズムが実現すれば、もっと多くの人が島を訪れるはず。収量はまだまだこれからですが、この国産コーヒープロジェクトが、徳之島の、そして日本のコーヒー産業に新たな1ページを描いていくことを願っています」

この記事は、Standart Japan第32号のスポンサー、味の素AGF株式会社の提供でお届けしました。
徳之島コーヒー生産支援プロジェクトにご興味のある方は、こちらからチェックしてみてください。