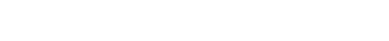Standart Japan 第29号のパートナーである Giesen Japan(ギーセンジャパン)が主催する「1st Crack Coffee Challenge(ファーストクラックコーヒーチャレンジ、以下1CCC)」は、ロースターが主役となり、焙煎技術だけでなく、その個性や想いが問われる競技会です。
若手焙煎士にフォーカスを当て、全国から集まったロースターたちが「再現性」「表現力」「個人のストーリー」を武器に焙煎技術を競い合います。焙煎という仕事の奥深さを浮き彫りにしつつ、コーヒーを「味」だけにとどまらず、「エンターテインメント」として社会に届けることを目指す本大会は、回を重ねるごとに注目を集めています。
第4回目の開催となる2025年度を前に、Giesen Japan に、大会に込めた想い、競技設計の背景、これまでの成果、そして今後の展望についてお話を伺いました。
今年で4回目となる1CCCですが、改めてどのような競技会なのか、開催の目的や背景にある想いをお聞かせください。
1CCCは、2022年にスタートした「若手焙煎士日本一」を決める競技会です。私たちギーセンジャパンは、「ロースターと共に成長する」ことをミッションに掲げており、この競技会を通じてコーヒー業界に新たな価値を生み出したいという想いから、本企画が始まりました。
これまでの開催を通じて見えてきた1CCならではの成果や課題について、印象的なエピソードとともに教えてください。
1CCCでは、焙煎の技術だけでなく、ロースター自身の想いを語っていただく「プレゼンテーション」も評価の重要な要素としています。2022年以降、3名のチャンピオンが誕生しましたが、彼らは焙煎士としての技術力はもちろん、人間性や熱い想いを併せ持つ、まさに「ファーストクラックらしさ」を体現する存在です。
2025年初頭には、歴代チャンピオン3名と共に国内のコーヒー農園を視察する機会も設けました。私たちは、優勝がゴールではなく、そこからさらに多くの経験やビジネスのチャンスを提供できるよう、継続的な関わりを大切にしていきたいと考えています。
若い焙煎士たちに競う場を提供するという点には、どのような意図があったのでしょうか?
今後10年、20年とコーヒー業界を牽引していくのは、現在のトップランナーだけでは難しいと感じています。新しい考え方を受け入れ、柔軟な姿勢でチャレンジできる若い世代の力が必要不可欠です。彼らに競う場を提供することで、業界全体に新たな風を吹き込みたいという想いがあります。

自社が取り扱う製品に限定せず、あらゆる焙煎機での参加を可能にしている点に強い理念を感じます。こうした“開かれた競技会”を目指す意図について、詳しくお聞かせいただけますか?
M-1グランプリが漫才の裾野を広げたように、私たちもコーヒーの世界を広げるために、業界に同様の大会が必要だと考えたのが出発点です。コーヒーを単なる「味の話」にとどめず、「エンターテイメントとしてのコーヒー」という新しい切り口を提案したい。そして、コーヒーに人生をかける人たちを、業界の外からも応援できるようなプラットフォームをつくりたいという想いが、この競技会の原点にあります。
この大会の予選では、競技者に発送されるモデル焙煎豆を各自の焙煎で再現してもらい、それを外部審査員によるカッピングで評価するだけでなく、科学的な評価も取り入れている点がユニークです。こうした審査設計に至った経緯や、その目的を教えてください。
私たちギーセンジャパンは、焙煎士の仕事とは「120点のコーヒーを一度つくる」ことよりも、「80点のコーヒーを継続的に再現する」ことだと考えています。だからこそ、「サンプル豆と同じ焙煎を再現する」ことを競技の中心に据えました。
また、第1回大会では審査員が120カップのカッピングを行いましたが、後半になると舌の疲労により正確な評価が難しくなったというフィードバックがありました。そこで、人間の感覚だけに頼る審査の限界を感じ、より客観的な評価方法を模索する中で、「コーヒーの成分を分析する」ことで科学的・数値的な評価が可能になるというアイデアにたどり着きました。総合スポンサーである味の素AGF社の協力のもと、他に類を見ない科学的プロセスを導入できています。
大会を継続していくことで、日本のコーヒーカルチャーのどのような発展に寄与していきたいと考えていますか?
プロファイルを選んでボタンを押せば「誰でも美味しいコーヒーが焼ける」時代は、そう遠くないかもしれません。だからこそ、私たちは「焙煎士の価値とは何か?」という問いを常に投げかけていく必要があります。1CCCを通じて、焙煎士が新たな視点を得て、それを実務に活かすことで、自身の成長、さらには業界全体の成長につながっていくことを願っています。

今年の大会について、注力しているポイントや新たな試みなどがあれば教えてください。
2025年度は、約20社のスポンサー企業様からのご支援をいただき、開催の運びとなりました。今年はコーヒーをよりエンターテイメントとして楽しんでいただけるよう、開催日を土曜日に設定し、一般の方も来場しやすいスケジュール・コンテンツを準備しています。
また、これまで予選のカッピングはクローズドな環境でオンライン配信のみでしたが、今年は競技者も参加できる「オープンカッピング形式」を予定しています。焙煎士同士の交流やフィードバックの機会をより多く提供したいと考えています。さらに、2024年度からはお隣・韓国でも本競技会が開催されており、今年は2回目の開催が決定しています。基本的なルールは共通ですが、決勝大会は各国ごとに行われます。ぜひこちらも楽しみにしていてください。
-----------------

2024年に開催された前回大会では、Standart Japan日本語版編集長の室本が決勝ステージの審査員の一人として参加しました。ここでは、その決勝大会を、ジャッジという立場から振り返ります。
2024年大会の決勝ステージで審査員を務められましたが、大会全体を通じて感じた特徴や、印象に残った点を教えてください。
決勝大会では、制限時間20分の中で「ウェルカムドリンクの提供」と「プレゼンテーション」を行い、その内容を競い合いました。審査は、私を含む4名の審査員が9つの評価項目に対して5点満点で採点し、総合得点で順位が決まるルールです。それぞれ異なるフィールドで活躍する審査員が集まっていたのも、多角的にジャッジをしたいという大会運営側の思いが汲み取れました。
決勝に進んだのは、いずれも個性的で、多様なバックグラウンドを持った6名のファイナリストたち。中には、まだ自身の店舗を持たず、イベントベースでバリスタ活動をしている方や、焙煎を始めたばかりという方もいて、まずその点に驚かされました。35歳以下という年齢制限を設けた“若手焙煎士限定”の大会であることが、1CCCならではのユニークな魅力だと改めて感じました。
審査員という大役は初めてで恐縮していたのですが、出場者の皆さんの真剣な眼差しや、それぞれが選んだテーマへのアプローチの多様さ、そしてプレゼンテーションを通じて伝わる熱量に圧倒されました。会場全体の熱気も相まって、非常にエキサイティングで魅力あふれる大会でしたね。
また、大会終了後には、出場者たちがドリンクをふるまう場面もあり、会場内ではラテアートバトルも開催されるなど、エンターテイメント性にも富んでいました。こうした形式のイベントは日本ではまだ少ないと感じていたので、今後ますます盛り上がっていきそうな予感がします。



若手焙煎士によるプレゼンテーションやドリンクの完成度について、どのように評価されましたか? 特に印象に残ったプレゼンや味わいがあれば、その理由とともに教えてください。
決勝大会では、ウェルカムドリンクのアイディアや抽出技術はもちろん、テーマに基づいたプレゼンテーションによって“表現力”も試されます。ファイナリストの皆さんは、クリエイティブなドリンクを作るだけでなく、自分なりの答えをしっかりとプレゼンに落とし込んでいて、非常に印象的でした。
評価にあたっては、スコアシートを軸にしながらも、競技者が今何を考え、これまでどんな経験を重ね、今後どこへ向かっていきたいのか——そうしたストーリーの部分にも注目して審査を行いました。ドリンクに関しては、私はプロのテイスターではないので、あくまで一人の消費者として「飲んでみてどう感じたか」を基準に評価しています。
特に印象に残ったのは、第3競技者・池田大輝さんが提供した、コーヒーと煎茶を掛け合わせたウェルカムドリンク。池田さんは「コーヒーは酸味と甘味、日本茶は甘味と苦味でバランスをとるので、実はとても相性が良い」と語っていて、その言葉通り、実際のドリンクも両者の魅力が見事に融合していました。
使用されていたのは、ケニアとエチオピアのブレンド。フローラルでシトラス感があり、まるでブラックティーのようなニュアンス。そこに水出しで抽出した煎茶を加えることで、一口目はとろりとした口当たりから始まり、コーヒーのフレーバーがふわりと広がった後、波が引くように煎茶の柔らかな甘みが立ち上がってきます。特に印象的だったのはアフターの余韻。コーヒーのフレーバーがグラデーションのように消えていき、煎茶特有の旨みとやさしい渋みが、心地よく残りました。あまりに美味しくて、自分でも再現しようとメモしてしまったほどです。ただ、他の競技者のドリンクもそれぞれに素晴らしく、正直、評価は非常に難しかったです。
プレゼンテーションで特に心を動かされたのは、2024年大会で優勝した第6競技者・立野慶太さん。彼は「サプライチェーンを“輪”に変える」というテーマを、自分の行動にどう落とし込むかを丁寧に紐解いていました。知らないことを恥じずに他人に尋ねること、仲間とアイディアを出し合うこと。そうしたプロセスの中で得た気づきを、まっすぐな言葉で伝えてくれました。
まだ20歳という若さながら、その熱量と真摯な姿勢には目を見張るものがあり、緊張しながらも観客の心をしっかりとつかんでいたと思います。これからのコーヒー人生の中で、彼が語ったその気づきをどんな形で実現していくのか、とても楽しみです。
とはいえ、皆さん本当に素晴らしいプレゼンテーションでしたので、ぜひ気になる方はYoutubeにも動画があるのでチェックしてもらいたいですね。
このような競技会が焙煎士に与える影響や、今後に期待することがあれば教えてください。
日本におけるスペシャルティコーヒーの歩みを振り返ると、その萌芽は2000年代初頭に見られ、2010年代には全国各地に個性あるロースターやコーヒーショップが次々と誕生しました。情報が今ほど整っていなかった当時、多くの先駆者たちは手探りで試行錯誤を重ねながらも、互いに情報を共有し、助け合いながら業界を築いてきた印象があります。時代の流れとともに、それぞれのブランドは成長を遂げ、ビジネスとしての規模も拡大。現在では、当時から活動を始めた現在30代後半〜40代のロースターたちが、日本のスペシャルティコーヒーシーンをけん引する存在になっています。
一方で、2020年代に入り、コロナ禍の影響などで業界全体が一時的に停滞した時期もありましたが、近年は再びマイクロロースターやスモールスタートのコーヒービジネスが増えてきたと感じています。その中には、まったく新しい世代のロースターも多く、若い世代がこの業界に新風を吹き込んでいるのが特徴です。
そうした中で、1CCCのような競技会が果たす役割はとても大きいと感じています。SCAが主催するバリスタチャンピオンシップなどの大会もありますが、競技会ももっと多様になっていいはずです。若手が挑戦できる「舞台」があることで、業界全体が刺激を受けて活性化されるだけでなく、新たな繋がりやコミュニティが生まれ、そこから面白いアイディアやコラボレーションも自然と生まれていく。そんな未来を想像するだけで、ワクワクします。
1CCCが若いロースターたちにとっての希望や目標となり、さらにはこの業界全体の可能性を広げる存在になっていくことを、これからも楽しみにしています!
2025年の1st Crack Coffee Challengeについては、大会公式のInstagramもチェックしてみてください。
この記事は、Standart Japan第29号のパートナー Giesen Japanの提供でお届けしました。